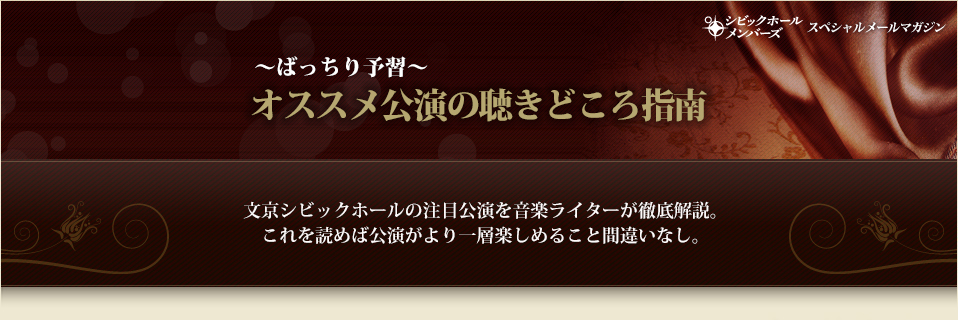![]()
![]()
レ・ヴァン・フランセ(Les Vents Français=フランスの風/木管)という、新しい時代を予感させるネーミングが映えるグループがデビューを果たしたのは2002年のこと。すでに注目のプレイヤーだった6人が結成したことで大きな話題を呼び、「スーパー・アンサンブル」「ドリームチーム」などの称号がメディアに踊った。結成15年を過ぎてもその新鮮な音楽は変わることなく、そこへ徐々にベテラン感が加わっていくというこのグループの進化は、おそらく日本の音楽ファンもよくご存知のことだろう。なにしろ彼らは2002年以降、何度も来日し、日本全国でコンサートを重ねてきたのだから。最年長は1956年生まれのジルベール・オダン(バソン=フランス式ファゴット)、最年少は1971年のフランソワ・ルルー(オーボエ)と、メンバー間では15歳の年齢差があるものの、世代間のギャップはまったく感じさせない。そのサウンドは明快な21世紀のフランスを象徴するものとなり、その上で個々のヴィルトゥオジティを尊重した自由なアンサンブルを繰り広げる。
レ・ヴァン・フランセは、21世紀になってオーケストラのサウンドなどがグローバル化(インターナショナル化)する傾向にある中、フランスの個性と伝統を残しつつ、新しいサウンドを創造する目的で活動している。彼らは世界的にみてもトップ・クラスのプレイヤーたちであるため、同業の音楽家からもリスペクトされる存在だが、吹奏楽やアマチュア・オーケストラを楽しむ管楽器プレイヤー、そしてピアノへ熱心に取り組む学習者にとっても憧れの存在であるはずだ。そうした方々にとって6人の演奏は理想であり、夢であり、目標となるべきものである。どのような音が美しいのか、アンサンブルとはどういうものなのか、フランス的なサウンドというのはどんな音なのか。そうしたことを知りたいという方に、彼らの演奏はいろいろなヒントを提供してくれるだろう。
もちろん、楽器は演奏しないけれど音楽を聴くのが好きだという方にとっても、極上の時間を提供してくれるのは間違いない。5つの管楽器が作り出す絶妙な音色とハーモニー、そこへきらきらと輝くような音を加えていくピアノ。まさに“フランスの風”を感じながら、その心地よさを味わえる時間。それこそが、レ・ヴァン・フランセのコンサートなのだから。

©wildundleise.de/Georg Thum
文京シビックホールでは2016年10月以来、1年6か月ぶりとなる公演だが、ロシア、ドイツ、フランスの作曲家による多彩な作品を演奏してくれる。その中で注目すべきは“掘り出しもの”といえる1曲、ルートヴィヒ・トゥイレ作曲の「六重奏曲Op.6」だろう。トゥイレはマーラーやドビュッシー、R.シュトラウスらと同世代の作曲家だが、この曲は第1楽章が始まってすぐに「あ、こんなにいい曲があったのか!」と驚いていただけるほどのものだ。「実はこれ、ブラームスの失われていた秘曲で……」と言われてしまうと、そのまま信じてしまう人がいるのではないだろうか。そもそもピアノ+木管五重奏という編成で書かれた曲が意外に少なく、プーランクの作品と共に重要なレパートリーとなっているのだ。レ・ヴァン・フランセも2014年に録音しており(『管楽器とピアノ~レ・ヴァン・フランセの真髄』と題されたCDで発売中)、最近では三浦友理枝(ピアノ)や上野由恵(フルート)ほか、東京の若いプレイヤーたちによって結成された「東京六人組」もCDでリリース。室内楽ファンや管楽器ファンにちょっとした話題を提供している曲なのである。だから、もし「トゥイレ、知らない作曲家だな」と心配している方がいらっしゃるなら、「大丈夫です。難しそうな音楽ではなく、とても素敵な曲ですから」と声を大にしてお伝えしたい。
クラリネットとファゴット奏者にとっては重要な作品であるミハイル・グリンカ作曲の「悲愴三重奏曲」(クラリネット+ファゴット+ピアノ)も、初めて聴く方には印象的な音楽となるだろう。題名には「悲愴(pathétique)」とあるが、聴いてみるとさほどシリアスな曲調でもなく、「心に影を落とすような」程度の印象だ。グリンカはオペラ『ルスランとリュドミラ』序曲があまりにも有名であり、なかなか他の作品をコンサートで聴けるチャンスが少ない。この15分ほどの三重奏曲は、穏やかなメロディが次々に現れるという作品だが、メイエ、オダン、そしてル・サージュの3人が演奏することでさらに磨き上げられた音楽になることだろう。
 ©Denis Felix
©Denis Felix
 ©Uwe Arens/Sony Classical
©Uwe Arens/Sony Classical
 ©Shin Yamagishi
©Shin Yamagishi


 ©Jean-Baptiste Millot
©Jean-Baptiste Millot
そしてもちろん、彼らのシンボル的な作品であり、これまでの来日コンサートでもほぼ毎回演奏され続けてきた、フランシス・プーランクの「六重奏曲」も聴ける。プーランクが1932年に発表したこの作品は(その後、1939〜40年に改稿)、ヨーロッパが2つの大戦の狹間にあって混迷を極めていた時代の産物であり、その不安感をやや反映しながらもパリの洒落た空気感を忘れずにいるという、独特な味わいをもっている。「疾走するメランコリー」という副題を付けたくなるような第1楽章は、ピアノにも5つの管楽器にも幅広い音域や繊細な表情を要求しているため、全員の演奏テクニックが見事にそろい、しかも絶妙なバランス感覚も必要だという難曲。やさしい微笑みを音楽にしたようなオーボエの主題で幕を開ける第2楽章は、他の楽器を次々と巻き込んでいき、コミカルで軽快な音楽へ(とてもプーランク的!)。さらに明るく、アクティヴな音楽となる第3楽章は、ホルンのヒロイックな吹奏ほか各楽器のソロイスティックな面が強調され、全員による聖歌風の音楽でフィナーレを迎える(プーランクは敬虔なカトリックの信者であったことを思い出す)。
もし今回、レ・ヴァン・フランセの演奏を初めて聴いてみたいという方がいらっしゃったら、とにかくこの曲は必聴だ。いや、もうすでに何度か彼らの演奏で聴いているという方にも「あの喜びをもう一度味わってみませんか」とお声がけしたい。彼らが飽きることなく何度でも演奏し続けるのは、おそらくそこに「進化」があるからなのだ。だからこそ「レ・ヴァン・フランセのプーランク」は輝かしいブランドであり続け、何度でも聴きたいという方がたくさんいらっしゃるのではないかと思う。
ほかにも、プーランクと同じ時代を生き、パリの香りを音楽に投影させたジャック・イベールの作品、そしてダリウス・ミヨーの作品も、レ・ヴァン・フランセにとっては手の内に入っているものであり、現代フランスにおける最高級の音とアンサンブルを楽しめる音楽でもある。こうした作品を聴くたび、筆者は「音楽における粋とはなにか」を考えてしまうのだが、彼らこそがその答えなのかもしれない。
結成して15年を越え、同じメンバーでありながらもマンネリズムをまったく感じさせない彼らの音楽は、やはり常に進化を続けているのだろう。だからこそ、それを味わうために何度でもコンサートへ足を運びたくなる。今回の来日公演、まだレ・ヴァン・フランセを聴いたことがないという方が周囲にいらっしゃったら、ぜひともお誘いいただき、文京シビックホールへ!

音楽ライター。音楽家のインタビュー記事、コンサートのプログラムノート等を中心に執筆。
『ぶらあぼ』『ぴあクラシック』『モーストリー・クラシック』『ショパン』等で記事を執筆するほか、クラシック音楽の魅力を伝える音楽講座なども担当。
著書に『ロシア音楽はじめてブック』(アルテスパブリッシング刊)。共著は多数。