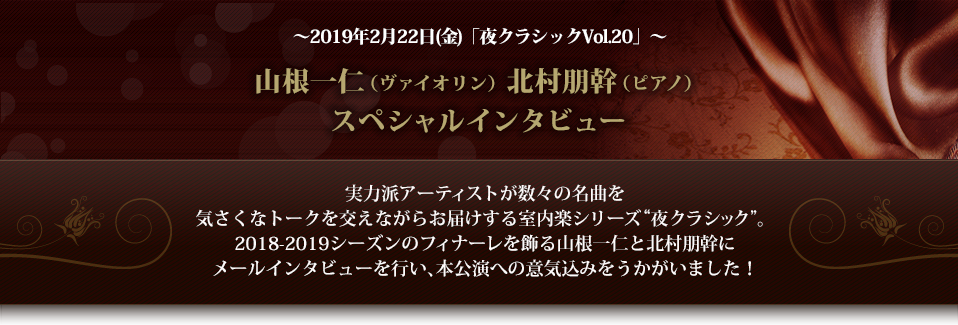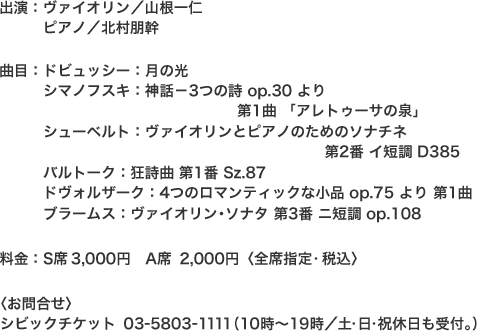©K.MIURA
©K.MIURA
![]()
1995年生まれ。2010年、中学校3年在学中に第79回日本音楽コンクール第1位、レウカディア賞、黒柳賞、鷲見賞、岩谷賞(聴衆賞)、増沢賞など5つの副賞を受賞。桐朋女子高等学校音楽科(共学)に全額免除特待生として迎えられ、2014年首席にて卒業。
これまでにバーミンガム市響、プラハ・カメラータ、N響、都響、日フィル、東響、札響、京響、アンサンブル金沢、名古屋フィル、大阪フィル等国内外のオーケストラと共演を重ねる。2011年第60回横浜文化賞文化芸術奨励賞最年少受賞。2015年青山音楽賞新人賞、第26回出光音楽賞受賞。第43回江副記念財団奨学生。
現在、ドイツ国立ミュンヘン音楽大学に在籍。クリストフ・ポッペン氏のもと、さらに研鑽を積む。
 ©TAKUMI JUN
©TAKUMI JUN
![]()
愛知県出身。これまでに東京音楽コンクールにおいて第1位ならびに審査員大賞(全部門共通)、浜松国際ピアノコンクール第3位、シドニー国際ピアノコンクール第5位、リーズ国際ピアノコンクール第5位、ボン・テレコム・ベートーヴェン国際ピアノコンクール第2位を受賞。
日本国内をはじめヨーロッパ各地で、オーケストラとの共演、ソロリサイタル、室内楽、古楽器による演奏活動を定期的に行っている。
東京藝術大学に入学後、ベルリン芸術大学ピアノ科で学び最優秀の成績で卒業。
伊藤恵、エヴァ・ポブウォッカ、ライナー・ベッカー各氏に師事。現在はフランクフルト音楽・舞台芸術大学に於いて、イェスパー・クリステンセン氏のもと歴史的奏法の研究に取り組んでいる。
![]()
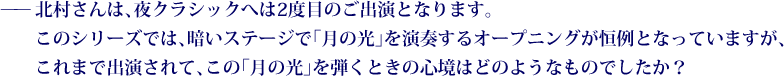
北村:夜や闇、そしてその中の光というものから数多の作曲家がインスピレーションを受けたのは、我々にはそれらをコントロールすることが絶対にできないからでしょう。だからこそ、闇の中に射す光は、奇跡や救いや夢などとして捉えられてきたのだと思います。
現代ではすでに、夜や闇というものの意味がまったく変わってしまいました。さらにこの公演では光の演出がなされる、つまり“人工的に”光を加えていくことになっています。前回演奏させていただいた際、不思議と聴衆の方々はこれをとても自然なものとして受け入れている感じがあり、そうなると自分もただの現象の一つとして存在しているような感覚になりました。
演奏するときは、どんな曲にも景色が見えています。それは架空の森みたいなもので、そこの景色はもちろん、気温、匂いまで全て思い描いています。それは僕が勝手に思い描いているものなのですが、その中に自分がいる状態が作れなくては、人前で曲を演奏することは絶対にできません。その意味で究極的には、演奏するのがどんな場所でどんな演出が施されていようと、あまり変わらないのかもしれません。
![]()
山根:北村くんとは18歳の頃から一緒に弾かせてもらっています。 彼の音楽からは、彼の持つ繊細な感覚やヨーロッパの香りを感じます。リハーサルでは豊富な知識を提示してくれて、それが音楽を創るにあたって大きな要素となっています。
北村:山根くんの演奏の魅力は、瞬発力や柔軟性、あとはやはり、羨ましいくらいのスター性でしょうか。僕たちは音楽的にも性格的にもほぼ真逆のタイプですが、特にこの数年は定期的に、いろいろな場所で、あらゆる形の作品で共演しているので、お互いの長所や短所、傾向や嗜好もわりと理解していると思います。
![]()

©K.MIURA
北村:彼には、不必要な気を遣うことなく意見を言うことができます。何度もリハーサルを重ねたいということにも賛同してくれていて、何日も続く彼とのリハーサルは、毎日違う結論に辿りつきます。そしてなんとか「これ以上はないだろう」というアイデアを共有した矢先の本番で、2人ともまったく予想しなかったことが即興的に起き、それにお互いが反応します。彼との共演では、そういうことがとても多いです。
山根:リハーサルは、多いに越したことがないと思います。 昨今の音楽界では、少ないリハーサルで演奏会をやり遂げることがプロフェッショナルというような風潮がありますが、これは決して理想的な形ではないと思います。北村くんも同じことを考えているので、二人で試行錯誤する時間、つまりリハーサルにかける時間が、必然的に多くなっています。
![]()
北村:リハーサルで最初に弾き終えたあと、こちらを振り返った山根くんから、「北村くん、悪くないじゃん。型にはまっていないのが良いよ」と言っていただきました(笑)。
これは笑い話として思い出すのですが、真面目に考えると、まさに先ほどお話した「即興的に反応し合う」演奏で、確かに悪くなかったのです。そのまま舞台に行くこともできる内容だったと思います。
でも、今はあくまで即興的に反応し合う演奏を前提として、その上で、二人で本番までに少しでも曲の本質に近づこうという取り組み方をしています
山根:初めて共演したのは18歳の頃なのですが、初めて会ったのは、僕が9歳、彼が13歳の時、テレビ番組「題名のない音楽会」の収録でした。
当時も今とかわらず、真面目そうな歳上のお兄さんという感じで、インタビューで練習時間を聞かれて「平日は5時間、休みの日は好きなだけ弾いています」と、サラッと答えていました。 一方僕は、その直前に僕なりに「1日1時間くらい(実際は30分強だけど)」…と見栄を張って答えていたので、その練習時間にびっくりした記憶があります。
![]()
北村:僕としては、冒頭に夜クラシックテーマ曲「月の光」を演奏すること大きいので、そこから現実に戻ることなく、さらに幻想的なシマノフスキの「神話」へ移行することによって、初めからずっと、ここではないどこかを漂っているような構成にしたいと思いました。
プログラムの中の別の曲が呼応して助けになるということは、ソロのリサイタルでも常に起こります。山根くんとのリサイタルでも、いつも、何かしらのテーマや繋がりを念頭にプログラムを組み立てています。
今まで彼とは、ブラームス1番、2番を演奏していますが、今回初めて3番に取り組むことになります。また、シューベルトは彼が提案してくれた作品です。あの本当に個人的な心象風景の旅のような音楽が、大きなホールでどのように表現できるのか楽しみです。
山根:僕にとっては、今回の曲はほとんどが初めて演奏する作品なので、かなりの挑戦です。 オーストリア~東欧というコンセプトで組んだプログラムで、その繋がりを音にするとどうなるのかという楽しみもあります。シューベルトのソナチネは、僕のお気に入りの曲です。本番はもちろん楽しみですが、リハーサルでどんな新しいアイデアが生まれるのかも、とても楽しみです。

©TAKUMI JUN
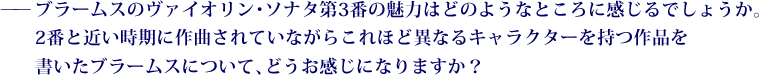
北村:ブラームスのキャリアの始まりとなった、ヴァイオリニストとの演奏旅行中に影響を受けたハンガリーの香り、当時出会い、もういなくなってしまった人達との合言葉「frei aber einsam(自由だが孤独)」のエコーなどからも、書かれるべくして書かれた最後のヴァイオリン・ソナタだと思います。そして、人生への心情のようなものを、音楽にこれほどそのままトレースすることは、ブラームスにしかできないことだと常々感じています。そこに感謝すると同時に、あまりにむき出しの心に、いたたまれなさを感じます。
数年前、ベルリンで古楽器を用いてブラームスのヴァイオリン・ソナタ全曲リサイタルを演奏しました。フランス人のすばらしいヴァイオリニストと、1ヵ月ほぼ毎日のように歴史的観点からの研究をし、リハーサルを重ねたことで、いろいろなことを知り、物事の見え方も大きく変わりました。
その時、最も印象に残ったのがこの第3番でした。当時の演奏慣習に関する文献を読み、彼らを継ぐ世代の録音を聴くと、この音楽の普遍的な自由さ、そして自由であることの哀しさを感じました。
古楽こそ本質だという考え方は嫌いですが、そこには、いわゆる現代の“お手本”には絶対に表現できないものがあります。ただ、我々が生きているのは21世紀です。現代の楽器とどう対峙し、表現していくか。ただのイミテーションではない方法は必ずあると信じています。
山根:僕は、第3番のソナタには、第1番、第2番とは違う、何かに憑依されているようなイメージを持っています。言葉にするのは難しいのですが、それはネガティヴなイメージというのではなく、ソナタという枠に収まらず、ブラームスの交響曲にも通じるものがあるという印象です。壮大な楽曲だと思います。
ブラームスのヴァイオリン作品を演奏するうえで理想としているのは、ブラームスの人間味あふれる音楽に沿った音を鳴らすということです。 それは、時に儚く、触れただけで崩れてしまいそうだったり、自分を鼓舞しようとしていたり、内に秘めた爆発的な何かだったり… 。同じ人間として僕がそれらを表現するということは、自分自身を表現することよりも難しい。でも、それこそが音楽を勉強する楽しさでもあります。
![]()
北村:近代的な響きのするピアノという楽器から、ピアノではないような音を出したいということは、ソロの時も常に願っています。
室内楽での僕の理想は、誰がどのパートを弾いているのかわからないくらい全てのパートが柔らかく溶け合って、1人の音楽のように成り立っている演奏です。柔らかくというのは、現実に鳴らされる音が柔らかいという意味ではなく、例えば、休符の人も他のパートを弾いていて、音を鳴らしている人も休符のパートであるかのような、そんなイメージです。
そのため、自分が演奏するパート以外も全てのパートを深く読み込んで、自分だったらどう演奏するか、弦楽器の弓順、位置やヴィブラートの大きさまで考えます。だからこそ、ピアノパートにも提案をしてくれる共演者とのリハーサルはとても好きです。
![]()
北村:深夜は文章を書いたり、本を読んだり、いろいろな物事を考えたりするのに最適な時間です。でも何より、真夜中に一人で映画を観るのは至福の時です。
山根:僕はこれといって特別なことはしていませんね。毎晩、クラシック音楽を聴いたり、YouTubeでお笑い番組を観たり、ラーメン店の紹介動画を観たりしています。
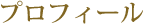
音楽ライター、編集者。大学院でインドのスラム支援プロジェクトを研究。その後2005年よりピアノ専門誌の編集者として、ピアニストや世界の国際ピアノコンクール等の取材を行う。2011年よりフリーランスとして活動。雑誌やCDブックレット、コンクール公式サイトやWeb媒体への寄稿のほか、「クラシックソムリエ検定公式テキスト」の編集などを手掛ける。著書に「キンノヒマワリ ピアニスト中村紘子の記憶」(集英社刊)。
HP「ピアノの惑星ジャーナル」