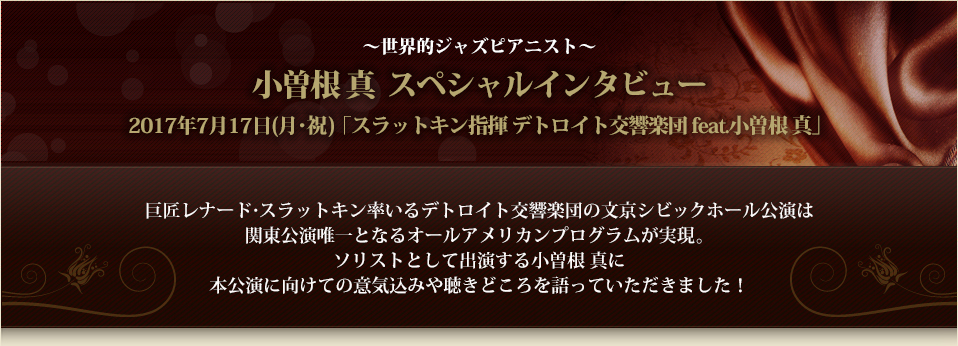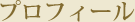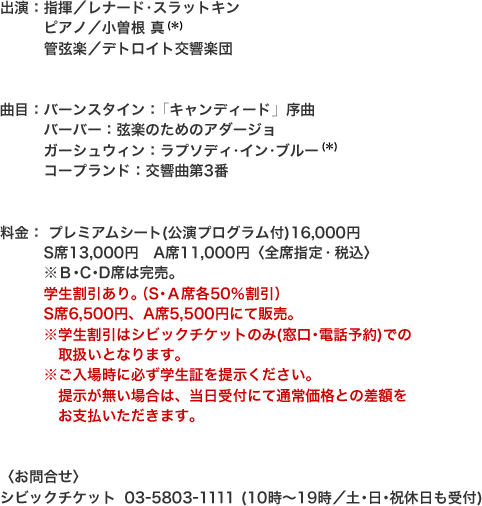![]()

©Shumpei Ohsugi
1983年にバークリー音楽大学ジャズ作・編曲科を首席で卒業。同年、米CBSと日本人初のレコード専属契約を結び、アルバム「OZONE」で全世界デビュー。2003年にグラミー賞にノミネート。
以来、ソロ・ライブをはじめゲイリー・バートン、ブランフォード・マルサリス、パキート・デリベラなど世界中のトッププレイヤーとの共演や、自身のビッグ・バンド「No Name Horses」を率いて、ジャズの最前線で活躍を続けている。
また、クラシックにも本格的に取り組み、国内外の主要オーケストラと、バーンスタイン、モーツァルト、プロコフィエフ、ラフマニノフなどの協奏曲で共演を重ね、「比類のない演奏で、観客は魅了され大絶賛した」(北独ハノーファー新聞)など高い評価を得ている。
2010年、ショパン生誕200年を記念したアルバム「ロード・トゥ・ショパン」を発表し同名の全国ツアーを成功させ、 ポーランド政府より「ショパン・パスポート」を授与される。
2014年にはニューヨーク・フィルのソリストに抜擢され、韓国、日本、ニューヨーク公演で共演。また、サンフランシスコ交響楽団にも招かれるなど、米国でも躍進を遂げている。
2016年5月には、チック・コリアとの日本で初の全国デュオ・ツアーを成功させ話題となった。2017年5/6月には、ゲイリー・バートンとの全国ツアーが予定されている。
近年は、作・編曲にも力を注ぎ、クリエイティブなオリジナル作品を次々と生み出している。
オフィシャル・サイト http://makotoozone.com/
![]()
![]()

「ラプソディ・イン・ブルー」って、難しい曲なんですよね。テーマとシーンが走馬灯のように変化していくので、気をつけないと展示会のようになって、単なる“ジャズっぽい曲”で終わってしまう。そうならないためには、ジャズやブルースからつながる一本の線を、演奏家がしっかり保つことが大切になります。
ガーシュウィンがこの曲を書いたのは、黒人のブルースを聴き、ホワイトカラーをはじめ多くの人々に、“みなさんの知らないこんなに素敵なエネルギーを持つ音楽がある”と紹介したかったからではないか、と僕は思います。ブルースを強く感じる冒頭の音階に始まり、人生やるせないことも多い、でも楽しくやっていこう、という前向きなエネルギーを昇華させる音楽が展開する。それが魅力ではないでしょうか。
そんな音楽のパワーを表現するため、毎回アドリブを入れて演奏するわけですが、回を重ねるごとに難しくなっていきます。つまり弾いていてこれは前にやったという考えが頭をよぎり、過去の即興の呪縛と戦うことになるのです。
でもこの10年ほどクラシックに取り組む中、もっと音楽の力を信じ、余計なことを考えず、頭の中で聞こえた音をそのまま鳴らせば良いと思うようになりました。“イタコ”みたいな感じで(笑)。即興演奏では特にそれが大事ですが、譜面に書かれた音楽でも同じです。
![]()
初めての出会いは、私が中学1年の頃、母が買ってくれたレコードを聴いた時です。正直、その頃は冒頭のフレーズが好きではありませんでした。ガーシュウィンがこの曲を書いた1920年代というと、ラグタイムやスイングより前ですから、あのイントロは、当時最前線のジャズを使って書かれたすごいものだったと思います。でも、中学時代の僕は、作曲されて50年ほど経ったこの曲の露骨なジャズの表現に“カッコ悪!”と感じてしまったのです。すでにその頃のジャズミュージシャンたちは、ジャズの響きをいかにうまくベールに包んで表現するかを追求していたわけですから。
でも、自分がジャズミュージシャンとして成長すると、あの原石のようなブルースのリフをどれだけ洗練された形で弾くことができるか、そこに挑戦するのが楽しくなり、自身が一歩前に進んだことを実感させてくれる曲となりました。
![]()
それは、“ラプソディ・イン・ブルー”の? それとも“僕のラプソディ・イン・ブルー”の(笑)? 僕の演奏については、即興でサーっとどこに行くかわからない旅を一緒に楽しむところですね。離陸は簡単ですが、その後どう着陸するかに注目してください。とは言うものの、これが簡単ではありません。ステージで弾きながら、耳と心は客席に置いて音楽を聴き、どこまで即興だったかわからないくらい自然にオーケストラパートとつながることが理想です。
人生と同じで音楽にもアクセントや驚きが必要ですが、奇をてらったり、狙ったりしているのがわかるとイタい。要するに、ステージから、コレどうですかと提示するような“上から目線”ではうまくいきません。お客さんの気持ちとリンクして、パッとタイミングを掴んでキメる。その瞬間を一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。

![]()
それが、僕がクラシックを弾く意味なのでしょうね。僕はあらかじめこう弾こうと決めていることはなく、相手がどう来るかによって生まれるケミストリーを音楽にしていくので、オーケストラもそれを楽しんでいるのだと思います。

僕がクラシックの世界で演奏できるのは、たくさんの方が胸を貸してくれているからこそです。だって、ジャズピアニストが、クラシック界の巨匠、レナード・スラットキンの指揮で、名門デトロイト交響楽団と共演するんですよ(笑)! おもしろいからやってみようと言ってくれる方がいるから実現しています。
新しいものと向き合うことこそ、人間が本来やりたいこと。そのような僕の挑戦をご覧いただき、元気になってくれるお客様がいらっしゃると、幸せです。
![]()
どこのホールにも音楽の神様がいらっしゃいます。文京シビックホールの神様は、なんだかとても温かいんですよね。広さを忘れ、客席とキュッと結び付く魔法が働いている気がします。会員になって通っているお客様も多いのでしょう、みなさんすごく音楽が好きだということが伝わってきます。おかげでステージに立ったときには、ちょっと居酒屋に入って周りの人と仲良くなってしまうような雰囲気というか(笑)、日常的な感覚で、みなさんと一緒にすばらしい音楽の世界に行くことができます。それはとても素敵なことだと思います。
![]()
“今鳴っている音”ですね。用意してきたものを出すのではなく、そこにある音楽から新しいものを創ってゆく。ジャズの場合は特にそう言えます。
そもそもコンサートは、予期せぬことが起きてこそであって、一番だめなのは“予想通り”(笑)。それはクラシックの演奏会でも同じではないでしょうか。
もしかしたら演奏中に携帯電話が鳴ってしまうかもしれない。そんなときは、またコンサートの“魔物”の仕業だな、どう対応するかが試されているのだと思わないと。
以前このような体験をしました。尾高忠明さん指揮、札幌交響楽団とバーンスタイン作曲「不安の時代」を演奏している時、終盤で突如、携帯電話が鳴り響き、その瞬間、2000人の客席が負の感情に包まれてしまいました。しばらく気にしないで演奏を続けていた次の瞬間、和音がさっきの携帯電話のメロディと同じキーだったので「あ、来た!」と思い、そのメロディをアドリブで弾いたら、客席の不穏な雰囲気がさっと笑いに変わったのです。その後のフィナーレは感動的なものになり、泣いているお客様もいらっしゃいました。ちなみにこの出来事は、翌日の新聞に載りました(笑)。
音楽を聴く(演奏する)、その原点は、予期せぬこと遭遇しながらも、自分の生を実感することだと思います。もちろん、人にはそれぞれいろいろな生き方があると思いますが、僕はそんな、予期せぬことも楽しめるような生き方がしたいですね。
みなさんも日常の中で、次々とアクシデントに見舞われることがあるかもしれません。でも、予想外のことが起きるのが人生、試されているのだと考えるほうが楽しいですよね。

![]()
音楽ライター、編集者。大学院でインドのスラム支援プロジェクトを研究。
その後2005年よりピアノ専門誌の編集者として、ピアニストや世界の国際ピアノコンクール等の取材を行う。
2011年よりフリーランスとして活動。雑誌やCDブックレット、コンクール公式サイトやWeb媒体への寄稿のほか、
「クラシックソムリエ検定公式テキスト」の編集などを手掛ける。
HP「ピアノの惑星ジャーナル」